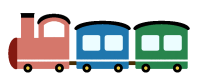なりそこないの国 -Falsaul’s birthday-
薄暗い世界で求めていた
この手が何も掴めなくても、
縋るものはあるのだと
この世界で求めてしまった
自分にもできることがあるのだと
このまま忘れていられたなら、
薄暗い世界が晴れることなんてないことを
自分が何もできなかったことを
知らないままですんだのに
*
目が覚めた時、世界は真っ白だった。
「……?」
周りを見渡すことはできても、視界はなんだかぼやけていて、ただただ白色の世界。自分の両手すらよく見えなかった。柔らかい物の上で寝ていたようでとりあえず上体を起こしてはみたが、少し位置が高くなった視界もやっぱりぼやけていた。
ここはいったいどこだろう。なんでこんなとこにいるんだろう。見えないこの世界はいったい何。──なんて思考は当時持ち合わせておらず、ただ見えない周りを見渡しながら放心していた。
しばらくすると、前方からガラガラという音が聞こえ、輪郭のぼやけた塊がこの空間に入ってきたことに気がついた。その塊は躊躇いなく、こっちへと向かってくる。そして、言ったのだ。
「おにいちゃん!」
「……え、」
「よかった! おにいちゃんも目が覚めた!」
この塊は紛れもなく自分へと言っている。正体不明の塊に、自分は困惑と同時に恐怖した。ぼやぼやではっきりしない塊がすぐ目の前に接近しているのだ。見えない、ということがどれほど恐怖を与えるのか身をもって体感した。
そしてその途端、今いる自分の謎の状況にも遅れながら恐怖と混乱が湧き上がった。見えない世界で自分だけ取り残されてしまったような、孤独感。
「だ、だれ……! おにいちゃんって、なに?!」
こわかった。見えない世界。どこかもわからない場所。いきなり現れた、未知の塊。
混乱はますます大きくなり、動悸までし始め息が荒くなる。落ち着いてなんていられなかった。
「おにいちゃん、わたしがわからないの……?」
「えっ?」
問いかけるその声は、自分と同様に困惑しているようにも聞こえた。しかし自分はその声の塊が言うように、この塊がなんなのかわからなかった。そもそも見えないし。聞き覚えだって、ない。
「おにいちゃん、自分のことはわかる? 名前は?」
「なまえ……?」
思わず復唱してしまうが、何を言っているのかさっぱりだった。〝なまえ〟? なまえってなんだ……。
……いや。名前。聞いたことある気がする。
自分は……、僕は──。
「…………わからない……」
考えた末、結局何もわからなかった。
名前という、自分を呼ぶ言葉があった気がする。そして、自分を呼ぶ誰かがいた気がする。いつのことなのかわからないのに。自分が知らない〝いつ〟というものがあるんだ。自分は最初からここにいて、今起きたわけじゃなくて。
いつからここにいるのか。どうしてここにいるのか。ここにいる以前は、自分は何をしていたのか。何かしていたのだろうか。自分の知らない自分が、たしかにいたんだ。その証が、きっと目の前の塊なんだ。
じゃあ、〝自分〟って、誰……?
「おにいちゃん、大丈夫だよ」
自分の中で繰り返される問答の中、ふいに降り注ぐ声にやっと自分の頬を何かが伝い濡らしている感触に気づいた。
「わたしも一緒だよ。心配しないで。そばにいてあげるから」
自分の手を握るのは塊のものだろう小さな手で、それは小さくも温かかった。孤独を感じさせるこの空間で、唯一の温もりでもあって、何も見えない自分を安心させるには十分すぎる救いだった。うるさく鳴り出していた鼓動の高鳴りも、少しずつ落ち着いていく。
「名前、は……?」
「わたし? わたしは□□だよっ。おにいちゃんのいもうと!」
〝妹〟で□□という名前らしいその塊としばらく話していると、また前方からガラガラという音がした。
「■■君!」
新しく入ってきたその塊は、ドタドタと迫り来る音を立てながら自分に近づいてきたと思うと、突然自分を包み込んできた。あまりにもいきなりのことでびっくりしたが、ふんわりと包まれる温かな心地は、なぜか嫌な気分にはならなかった。
「■■君わかりますか? お母さんですよ」
「おかあ、さん……?」
その言葉もまた、どこか聞いたことあるような気がした。そして呼ばれた■■という言葉が、さっきは思い出せなかった僕のことなんだと──僕の〝名前〟なのだとわかった。
入ってきたのは〝お母さん〟と〝お父さん〟と〝お医者さん〟と呼ぶらしい。僕の状況についてお医者さんが色々説明してくれた。
当時はよくわかっていなかったが、ここは病院という施設の一室で、僕は数ヶ月前に事故に遭い搬送されたらしい。そして事故の影響で、記憶喪失になってしまったとのことだ。自分のことも目の前の存在のこともわからないのはそのせいだと、お医者さんは言った。
お医者さんから軽く診察を受けると、
「■■君、これで見えますか?」
「……あ……」
僕の目に異常があることがわかり眼鏡という物をもらった。それを通して見た世界は、最初見たものとは比べ物にならないほど鮮明に映った。自分の両手も、ちゃんと見える。ぼやぼやだった塊もちゃんと輪郭があり、そばで見上げる小さな塊だった□□は僕と目が合うとにっこりと笑った。
「目が悪かったなんて……」
「これも事故の影響でしょう。まだ仮の眼鏡になるので、また詳しく検査したら新しい眼鏡を新調しますね」
眼鏡をもらった僕は改めて周りを見渡す。
この空間は、眼鏡を掛けても白かった。部屋という四方や上下は白色で囲まれ、僕が寝ていたこの〝ベッド〟も白色。ベッド脇には小さくも、しかしまた白色をした小棚と、ランプがある。どことなく眩しい。
周りを再確認した僕は自分の手を前に出し、握り、そして開く。いまいち自分の手だという実感が湧かなかったのは、記憶喪失になってしまったからだろうか。白色の一面の中で白色をしていない〝窓ガラス〟に顔を向けると、そこには自分が映る。窓に映った人物が自分であるという認識もその時はまだできなくて、首を傾げ、まばたきを数回して、寸分違わず同じ動きをするその〝相手〟に対して僕は手を振った。
僕はそれから詳しく検査を受け、自分自身や□□、お母さんやお父さんに対する記憶だけでなく、知識というものも欠落していることがわかった。言葉を聞いたり口に出すことはできるが、文字の読み書きができない。そして、言葉の意味すらも、わからないものがいくつもあった。記憶喪失になっても言葉を発したり、言葉のニュアンスをなんとなく聞き取れたのは、生まれてから今まで見聞きしたものの情報から脳が記憶しているかららしい。特に日常的に耳から入る情報は残りやすいのだという。
一ヶ月入院して教育とリハビリというものを受け、記憶と視力以外は特に問題なく僕はめでたく退院した。
退院後は家に帰って今までの生活というものを過ごすのだが、家を見ても庭を見ても、何も思い出すことはなかった。
「ここが我が家ですよ。なにか憶えていますか?」
お母さんに手を引かれながら告げられる。期待しているのだろうか、にこにこと明るい笑みを見せている。僕は何も答えられなかった。
「いいんですよ。これから一緒にわかっていきましょう」
お母さんは笑顔を崩さなかった。懐かしい気もしなくはないけど、これといって僕が過ごしていた記憶は浮かばない。
しいて言えば、庭の木に止まり鳴いている黒い鳥を見た途端、なぜだか無性に胸の奥を何かが掴む感覚がしたくらいだった。不思議でいて、不快でもあるざわざわとした感覚に僕は目を背けた。
二ヶ月ほど経った春先に、僕と□□は家庭学習を経て学校に通うことになった。学校は、僕が目を覚ました病院よりも北にある施設で、主に勉強を行う場所らしい。学校に通うことに義務があるわけではないが、勉強したい子や、親の勧め、同年代の子と学んだり遊んだりする公共の場として、通う子供は多いみたいだ。
そして学校には特別学級というものがあり、僕のように記憶を失って元の生活に戻るのが困難な子供や、身体的、精神的等の事情で普通の子と馴染みにくい子のための学級がある。僕と□□はその特別学級に入るんだそうだ。なんで□□も特別学級なのかはわからないが、僕一人じゃ心配だからだろうか。正直、記憶も無く誰一人も思い出せない僕にとって、いきなり色んな人がいる場所に一人で行くより、□□がいてくれるのは心強かった。
それなら記憶を失くす前の僕は学校に通っていたのだろうか。知り合いなどはいたのだろうか。疑問に思ってお母さんに訊いてみたら、
「■■君は学校に通っていませんよ。最低限の学習はしていましたし、家での手伝いや□□ちゃんの遊び相手をしてくれていたんです」
と返された。僕に学校での知人はいないらしい。
学校に通っていなかったのなら、学校以外での知人はいたのだろうか。僕のことを知っている人はいるだろうか。
そう考えていると、退院した時、近所のおばさんに声をかけられらことを思い出した。……うん、それくらいかな。