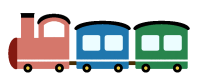偽人 -Falsaul-
昔々、とある研究好きの人間がいました。その人間は、たとえるならば小鳥。籠の中に入った複数の小鳥の中の一羽。そして、外を知りたいという好奇心を持った小鳥。
その鳥は籠を出て、外に出ました。初めて触れる外の世界に喜びを感じる、そんな人間。
何が起こるだろうという恐怖心を抱かず、何があるのだろうという好奇心が人間を動かしたのです。その好奇心がある神聖な洞穴へと導きました。知るならば立ち入らない。敬うならば立ち入れない。そんな洞穴に。
「なんだか緊張する。こんな気持ち初めてだ」
初めてのことがよほど胸を高鳴らしたのでしょう、人間は歩みを緩めませんでした。
──だけど知ったの。ここが何なのか。
人間は突然歩みを止めた。気配を感じた。身の毛もよだつほど大きな、そしておぞましい気配を。恐怖心を抱いていなかったその人間は、ここでやっと恐怖を知ったのです。汗が流れ出し、足は震え、戻ろうと思ってももう戻れない。まるで金縛りにでもあったかのように、体は固まってしまった。
『なんと礼儀のなっていないものか。主は我を前にやっと恐れをなすか』
人間の目に、二つの青く光る眼が映った。ギラリと鋭く、神々しく眩く瞳。
『さて、無礼をはたらく無知なモノよ。それなりの覚悟はしておろう。我に身を捧げるか? それとも、死を受け入れるか?』
洞穴の主はくすくすと嘲笑うように口を開けた。すると、
「何を言います? たしかに私めは無礼をはたらきました。それについては謝罪申し上げます。ですがあなたに私の命は奪えない」
先ほどと打って変わり、またもや好奇心に導かれるような爛々と輝く瞳を人間は見せた。恐怖などもう無い。
『主はおもしろいことを言うな。何故そう思う』
「あなたはとても優しい目をしている。そう、とても。そんなあなたが私の命を奪うなんて考えられません」
『…………』
人間はそう述べて笑った。なんて根拠の無い自信だろう、洞穴の主は唖然とし何も答えられなかった。しかし人間の恐怖が消え去った堂々たる出で立ちは、ある意味は愚かで、ある意味で純粋でもあった。
そんな奇妙な人間に、洞穴の主は興味を持った。
『……ふふ、ふははっ! はあ、なるほど。ふふ……、よいよい。主よ。我は主を気に入った。他のモノは我の気配だけで去るというのに、主は我に会いに来た。迷いなきまっすぐな心が我が地へ導いた。主のその心、大事にせ。珍しきヒトよ、我は主ともっと語ろう。主の話も我に聞かせよ』
それからというもの、その人間は毎日のようにここへ訪れた。ずっとひとりで過ごしてきた私には、それがとても新鮮で退屈のしない日々だった。私の知識を与えたり、国の中のことや人間の世間話を聞いた。
ある日、人間はこう話した。
「普通の動物もあなたと同じように会話ができたらさぞ楽しいでしょうね」
「傲慢なやつめ。他の生き物にヒトの言葉を喋れというのか」
「……たしかにそれもそうですね。自分から寄せる努力をしないと」
そう言って笑った。
好奇心の塊を映し出した眼。動物と話がしたいという我が儘はきっと消えることはないのだろう。
「私はとある研究をしています。動物を人間に変えられないか、という研究を。でもあなたとお話しして気づきました。そんな身勝手なこと、何も知らない動物にできませんよね」
「…………」
「それでは私はそろそろ帰らせてもらいます。今日もありがとうございました」
その時見せた悲しげな表情を、今でも鮮明に憶えている。人間にとってそれほど憧れであり、夢でもあったのだろう。たとえ傲慢で生き物に対する冒涜だとしても、長年夢を見続けていたのだ。それが、打ち砕かれてしまった。私によって。
純粋な好奇心は残酷だ。
籠の中の鳥は外に出たかっただけ。外を知りたかっただけ。籠の外への扉を開けるためにどれほどの犠牲を生むのかも知らない。その犠牲の上で出る外はそれほどに気分のいいものだろうか。足元を見下ろして、いつか後悔することだろう。いつだって、気づくのは遅いものだ。
だから私は──
「人の姿には変えられる。だが人間にはなりきれない」
この身を以て〝研究の結果〟を見せた。
「……服が……必要ですね」
それが人間の求めていた研究の果てに対する感想の第一声だった。
傲慢さに気づきやってはいけないと頭で理解しても、結果を知らないまま憧れだけ抱き続けるのは苦痛だろう。叶うかもしれない可能性に縋ることは容易なのに、それを実践できず眺めるだけなのだから。
籠の外は素晴らしいものに見えるのに、外に出る手段も知っているのに、外に出てはいけないという決まりに縛られ籠の中でただ外を見続けるしかできない鳥と同じだ。外がどれほど厳しい世界とも知らずに、憧れ続けるのだ。
だから私は私を代償に、鳥が得たはずだった外の世界を見せてやった。
私の力であれば人になることくらい容易いが、それは人間の為す研究ではない。あくまで人間が自らの研究によって到着したであろう形を見せた。姿だけ見れば人間にも見間違うが、実際には目の色が違った。そして身体の造りも異なった。この造りは、生き物が成すはずの時間の経過の妨げをする。この存在を人間なんて言えるだろうか。偽の人でしかない。そもそも一般的な動物とも、言い難い。
私と会わなければ人間は研究を続け、最高でもこの最悪な結果を起こし後悔しただろう。動物を紛い物の存在に変えてしまったことにも、動物を実験材料にしてしまったことにも。この純粋で心優しき人間はそういうものだ。
叶えようと進むはずだった先は無駄な行為しか残らないことを理解させきっぱり諦めさせたかった。こんなことをするために現を抜かすのは愚行だ。外の世界は、憧れを抱くに値するものではない。
「なぜ、このようなことを?」
「未練がましい顔をしていたから真実を知らしめたまで。あとはただの気まぐれだ。我が談笑の相手を務めた奢りでも思え」
「気まぐれ、ですか」
「……なんだ」
「いえ、なにも」
これ以上私の気まぐれについて言及しようとせず人間は笑った。そう、ただの気まぐれだ。私にとっては愚かでも、人間にとってはかけがえのない夢。それを壊してしまったことには変わらない。本来私が干渉すべきではなかったのに。私の行為は気まぐれの贖罪にすぎない。同時に、人間の無謀さを理解させたかった。これは私の奢りだ。わずかながら私が人間と対等に話をしたくなった、というくだらない戯言をも思ってしまったがそれは気まぐれのついでにすぎない。
人間は研究をやめたものの、動物から人間へはどうやって変えられるのかと興味津々だった。原理や理屈が知りたい。構造が知りたい。欲望が尽きない人間の業。私の姿に満足したのか改心でもしたか、人間は知識を得ても研究を再開する気がないことが見てとれ一つ一つ教えてやった。人間もまた私の話し相手を付き合い続けてくれた。
穏やかな日々だった。いつぶりの安らぎかわからない。人間の寿命が短く儚く、この日々が長く続くわけではないとわかっていた。それでもできるだけ長く、この人間が飽きるか死に至るそのときまで、この日々が少しでも長く続けばと思った。
……思ってしまったのだ。
『バケモノ』
なんて愚かだったのだろう。私は人と相容れない。
ある日籠の中の者どもは、毎日のようにここへ来るこの人間を怪しんで跡をつけてきた。そしてその人間たちは、紛い物の姿を成す私の存在を受け入れられなかった。元々、好奇心の塊である人間の研究に対して快く思っていない者たちだった。本来ならそれが正しかった。私ですら、その研究をやめさせようとしたほどだ。だから仕方ないことだった。
私は畏怖すべき研究の結果の産物で居続けていたのだから。
人は人と違う得体の知れないモノに恐れをなす。己の身を守るための防衛本能。自分より巨体なものが相手なら勝ち目がないと判断し退避することもあるが、目の前にいるのはヒトの皮を被った成人ほどの大きさをしたバケモノ。勝算があると見えるなら、立ち向かうくらいの行動はするだろう。人間は自分を棚に上げ、優位であり続けないと気が済まない生き物なのだから。未知のモノは、それほどに恐ろしい。反抗しないよう、反抗させないよう。自分たちが覚えた恐怖を相手に植え付け恐怖させ、自分たちの立場が上だと言い聞かせたいのだ。
殴って。蹴って。這いつくばらせて。散々痛めつけたら杭を打ちつけて。鎖で縛り付けた。
罰なんだろう。
『私はお前らを忘れない──!』
傷を負った私は元の姿に戻れなくなった。
身の程を弁えず人間に近づき過ぎてしまった私の罪。
いつの間にか愚行を犯したのは私の方だった。