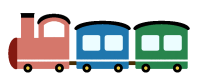鏡の国 -Recollection-
夏。虫の音が轟く森の奥地では、大きな湖が空に浮かぶ星月を映し出している。
その畔で、旅をし続ける小さな子供が一人、湖に顔を覗き込んでいた。
「……くそが……」
旅人は湖に映し出された自分の顔を消すように石をボチャンと投げ入れると、側に置いておいた持ち物の中から包帯を取り出して自分の頭をぐるぐるに巻いた。目と鼻の穴だけを残して、顔面を覆い隠すように。
そしてこの満天の空の下、虫の音に包まれながらも、旅人はひとりという孤独を身に感じ眠りに入った。
忘れられたらどんなに楽か
思いを知らずに私は祈る
忘れられない私があなたを縛る
あなたはどんな思いで私を呪う
来る日も来る日も忘れられないものがある
あなたの顔だけは忘れてしまったのに
夜が明けて日が昇る。太陽の位置はまだ低いが、光は森を通り湖をキラキラと反射させている。
旅人は目を覚ますと、頭に巻いた包帯を解いて肩ほどまで長さのある後ろ髪を左右に分け耳の下で縛った。
湖に近づき顔をバシャバシャと洗い、湖に映った自分の顔を見ると眉をひそめながら笑う。
「夢はもう終わりだ」
荷物をまとめて布袋に詰め込み、それを背負うと旅人は森に入って突き進んだ。
茂みを掻き分け草を踏みしめ、しばらく歩くと木々の捌けた道に出た。右と左、どちらの方向へ行こうかと悩んで下に落ちていた木の枝を拾うと、枝の端を地に着けてバッと手を離した。支えをなくした枝の先端は右でも左でもなく、真ん中に倒れていった。倒れた方向へ進もうと思っていたのだが、これだとどちらへも進めない。真ん中を進んでまた森に入る、ということも可能だが、そんな選択肢は無かった。
もう一回やるか、と旅人は面倒くさそうに屈む。すると右手の方から地面を鳴らす音が聞こえた。
顔を向けると音の正体が姿を現す。馬車だ。
「どうどう。ここで一体どうしたんだい?」
馬に付けられた手綱を操り、車体に乗ったヒゲを生やす男が旅人に声をかけた。
旅人はマントに付いたフードを被って顔を隠しながら返す。
「ちょーっとね。それよりおっさんどこ行くの」
「おじさんはこの先の国まで後ろの人らを乗せていくところだよ」
「へぇ。オレも乗せてよ」
「悪いけどタダでは……」
「金ならあるよ」
旅人は袋から金貨を二枚取り出し男に渡した。
「これでいい?」
男は目を丸くして思わず金貨と旅人を交互に二度見する。怪訝そうにも金貨を受け取り、車体の後ろを親指で差した。
「乗りな」
「へへ、あんがと」
旅人はニッと笑って車体に乗り込む。
中には色んな人がいた。大きな荷物を所持する男組。赤子を抱きかかえる母親と父親らしき寄りそう男。乗り口の隅でぽつんと座る白いフードを被った緑の服の子供。
旅人は緑の子に近づいて言った。
「隣、座っていいか」
「…………」
緑の子は顔を上げたが、すぐに顔を下げフードをぎゅっと片手で掴みながら首をぶんぶんと横に振る。返答はノーのようだ。
「なんだよ」
眉間にしわを寄せて旅人は緑の子の向かいの隅に座った。
車体が動き出し、ガタゴトと揺れる。あまり心地いいものではなかったが、疲れているのか 旅人はうとうとしながら寝てしまった。
数時間が経ち、旅人はいつの間にか熟睡していた。馬車がすでに止まっていることに気づかず、馬を引いていた男が旅人の両肩を揺する。
「ほらキミ。着いたよ」
「んんん……」
旅人は重そうに瞼を開け、目をこすりながら大きなあくびをし体を伸ばした。辺りを見渡すと乗客は自分以外いない。
「あれ……」
「国に着いたよ。降りるかい?」
「ああ、着いたんだ……。うん降りるよ」
旅人は立ち上がると荷物を持って、よいしょ、と馬車から飛び降りた。
振り返って男に礼を言いながら手を振り、目前に広がる大きな国を見やるれば、いまだ寝ぼけ垂れていた目がようやく大きく開かれる。
「ほぉう」
あまりの大きさに感嘆が漏れた。
入国すると国内はとにかく鏡が多い。歩く石畳の地面さえピカピカに磨かれ、まるで鏡のように自分が映っている。鏡の他にもガラス工芸品が多く、目にするもの全てが眩しいほどに輝いていた。くわえて今は昼時。真上から照らす陽の光によってどこもかしこも反射し放題。よく見なくとも目が眩みそうだった。
フードを深く被り直し、旅人はひとまずレストランへと足を運んだ。外は反射で眩しかったが、店内は天井に吊り下げられたシャンデリアが眩しい。床も当たり前だが綺麗に磨きあげられ日頃の掃除の苦労が思いやられる。
注文した運ばれてきた料理はというと、また当然のように見映えよし、味よしで文句の付けようがなかった。豪華なもてなしに王宮にでも来てしまったのかと錯覚するほどだ。
全てにおいて完璧すぎるため、入ってしまったのは高級料理店だったのだろうかと腹を括ったが、値段はそう高いものではなかった。心做しか肩の荷が下りた旅人だった。
「お気に召しました?」
「まあね。店も綺麗だし、料理もうまかった」
「綺麗……とは鏡のように、ですかな」
「え? まあそうだね。まるで鏡だ」
「左様ですか! それは光栄です! 一日三十以上の掃除は欠かしませんからね」
「へぇ……三十以上……」
鏡のように綺麗だと言っただけで店員は大層喜んだ。嘘はついていないのだが、その喜びように旅人は怪訝がりながら店を出た。
「鏡、か……」
この国は鏡を愛してやまないのか、国産品か、詳しいことはまだわからないが関係あることはたしかだろう。
腹ごしらえを十二分に済ませたところで、旅人は一旦手頃な宿を見つけ、荷物を置いてから観光することにした。
適当に見つけた宿は、やはりホールに鏡があちこちに飾られている。床も壁も階段も、綺麗すぎて宿全体が鏡のようだ。チェックインを済ませて部屋に入ると、部屋の中の小さなテーブルの上に説明書のようなラミネートされた紙が置いてある。紙には従業員が掃除に来る時間、シャワーを使用したり部屋で何かを食べたりした後はすぐ従業員に掃除の連絡を促すこと、大半が掃除のことについての内容が記されてあった。
「綺麗すぎもここまでくると病気じゃないかと疑うよ」
旅人は鼻で笑いながらポイと紙を捨て去るようにテーブルの上に放った。
窓から外を一望してみると、光を反射する国全体がまるで一つの芸術品のようだった。その中でも特に旅人が気になったのは、見える景色の中で一番大きく高いドーム状の建物。
「明日はあそこに行ってみるか……」
今から行っても日が暮れてしまう距離だ。公共機関があればそれを利用した方がいいだろうなと考えを巡らせる。今日のところはこの周辺の地域を散策してから明日あの建物に行こうと予定を立て、再び外に出た。
鏡専門店。ガラス専門店。アンティークショップ。この国の人の技術はたいしたもので、高級感漂う優雅な装飾を施した雑貨が多く目移りをする。売り物だけでなく、建物の外壁や街灯にも花や蔓をあしらった装飾や彫刻が施されていたり、道歩く人々も自身の身だしなみに気をつけているのか煌びやかでおしゃれな服装をしている。旅人の服装は簡素でフードの付いたマント、マフラー、左右で袖の長さが違う服に短パンに草履。そして背には焼き鳥の串を大きくしたような木製の物を背負った、あまりにこの国とは不釣り合いな簡素で奇妙な格好だ。しかしありがたいことに国民は旅人のことを白い目で見ることはなく、むしろ朗らかに微笑んで挨拶をしてくれる。待遇まで感服してしまう。明日行く予定の建物について聞いてみると、あれは国の代表的な科学博物館らしく、ぜひ行ってみるといいと口を揃えて勧められた。
適当に店を見つけ夕食を摂った後、旅人は宿に戻ってシャワーを浴びる。浴室に張られた鏡は結露防止でもしてあるのか湯煙をどれだけ浴びても水滴がつかず、対面するものを綺麗に映し出していた。この国の鏡への愛護心、あるいは身なりの注意によるものだろうか。
そんな散々歩き回って目にしたお国柄に染まることはなく、旅人は無慈悲な顔でシャワーを鏡に向かってかける。濡れて水の波がゆっくりと流れ落ちる鏡。水の波のせいで鏡は旅人を鮮明に映すことができなかった。
部屋を真っ暗にして旅人は頭に包帯を巻いてベッドに入り込む。シャワーを使用したら連絡しないといけないことを思い出し、面倒臭そうに横になったままベッド近くの電話機を取って連絡を入れる。連絡を受けた従業員が早くも一分後にやって来て部屋の電気をつけたが、旅人はシーツを頭から被って気にしないふりをした。従業員はてきぱきと仕事をこなし、一分も経たない間にシャワー室の掃除を終わらせた。『失礼しました。ごゆっくりおやすみくださいませ』という声をシーツ越しに聞きながら部屋の電気が消えたことを閉じた目から感じ取る。
静まり返った暗い部屋の中、シーツに包まった旅人は、今日も一人孤独だ。