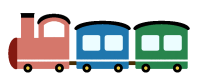森の主 -A little, little legend-
森が生まれたのは遥か昔。二つの命が共に生き続けたことで築き上げられた。いつしか一つの命は久遠を捨て、もう一つの命だけが森と共に残った。残された命は新たな命を育み、新たな命は森を守る主となる。そうして継いでいく森の記憶。
とある時代、一匹の白蛇が生まれた。
加護という名の近寄りがたきオーラ。生まれながらに他の生き物から崇拝され、白蛇は自分は偉い存在なのだと森を自由に生きた。
『我はこの森の主なるぞ』
白蛇に逆らう者は誰もいない。白蛇は自分に力があるのだと過信した。
森の中心には人間の住まう領域がある。白蛇は、自分には森全体を見守る役目があるのだと、人間の領域にも踏み込んだ。
只ならぬ風貌。恐れを知らぬかのような凛とした佇まい。人間たちも白蛇のことを特別な存在として崇め讃えた。
人間の領域から東側の森で白蛇はよく体を休めており、人間は白蛇のために祠を建てた。
幾年と時は流れ、未だ朽ちることを知らない身体の白蛇。今日もいつものように森を見回り、森の西側に着いた。
木々が捌けた空間に、ひとつの洞穴。
『さあ今日こそは我を讃えてもらおうぞ。いつからここに住んでるかもわからぬ人の子よ』
白蛇が洞穴に入ると、そこには人が一人いた。年は十代後半くらいだろうか。
「……偉そうな口ぶり。お前は何もわかっていない」
『わかっていないのは主じゃろう。我を誰と思うてか! 我はこの森と森に棲む子らを見守る役を担う森の主なるぞ! 特別な存在じゃ!』
「はいはい森の主様。森の主様がなぜこのようなつまらない場所へ?」
『その態度じゃ……。その無礼な口を今日こそは封じたろうて! 我に跪け! 我を讃えよ!』
人は眉をピクリと動かし、じろりと左の目で冷徹に白蛇を睨んだ。
「いまだ無知に生きる小さき未熟な魂よ。お前が何を言おうと何者と語ろうと自由だ。私には関係ない。だが、一つ忠告しておこう」
その目は青色に鈍く光った。
「自惚れるな」
空気がピリピリと痛い。体の自由を奪うかのような空気の重さ。呼吸することも忘れ白蛇は硬直した。
白蛇は人の気に圧され飲み込まれ、一滴の冷や汗を垂らしてようやく身動きできるようになるが、畏縮してしまい何も返さずゆっくりと身を引くことしか行動を取れなかった。
このやり取りが何年と続き今日に至る。
白蛇は自分が人より上の存在なのだと示そうと度々この場所に訪れるが、結果として認められたことは一度もない。唯一、この洞穴に住む人にだけ。
諦め祠に戻る白蛇。祠には数人の人間が待ち構えていた。
供え物を捧げたり、ご利益を求め拝みに来る人間は珍しくない。白蛇はただ、真面目な者だな、と思いながら近づいた。
不審と抱くことも知らずに。
これは罰だ
この森に異端者を招き入れた私の業
ここに決めよう
異端者に近づき過ぎた哀れ者
それは私だけで十分だ
私だけで十分だ
ここに踏み込んではいけない
互いに干渉を求めてはいけない
この森で生きるために
異端が共に生きられるように
みな、同じように生きるために
約束をしよう
「はぁ……はぁっ」
「待て!」
「はぁ……ぅっ、……ぁ、はぁ」
森の中の人間が住む領域。そこでまっすぐに足を運ぶことができずぎこちない足取りで走る白い髪をした少女がいた。少女は自分の身に纏うものを何もしておらず裸の状態で、頬の下には深い青色をした逆三角形の模様が入っていた。
彼女を追いかけるのは複数の人間。少女がこの領域から逃げようと森の中へ入ると、人間は足を止めた。否、止めざるを得なかった。
木々の陰から全身毛で覆われた巨体な獣──熊が現れたのだ。グルルルと唸る熊は口を半開きにさせ涎を垂らし、人間たちを小さくも鋭い眼光で睨みつける。まばたき一つ、指一本でも動かせば今にも襲いかかってきそうな熊を前に、人間は恐れを抱き身動きが取れなかった。
人間がこれ以上来ないことを確認すると熊は背を向け、ゆっくりとまた森の中へ戻っていった。少女は木に手をついて息を切らしながらその様子を見ていたが、戻ってきた熊と目が合う。熊は少女と森の奥を交互に視差した。
『ついていけばいいのか』
そう感じた少女は熊の鼻を撫で、共に歩みを始めた。
歩き続けて夜になり、いつしか雨まで冷たく降り出した。滴は少女の体温を奪っていく。足はぼろぼろで歩くのさえやっとだ。時折足を絡ませたり地に躓き転ぶが、熊は少し先を進んで少女が起き上がるのをじっと見つめて待つだけ。誰も少女のことなど助けてはくれない。自分で歩くしかなかった。
熊に誘われ訪れた場所は洞穴だった。熊は少女の背を頭で押し、先に進むようにと促す。少女が一人で進み始めると、もう自分の用は済んだと言わんばかりに熊は去っていった。
洞穴に入って雨は遮られたが、ひんやりとした空間に少女の体温が戻るわけもなく、体を震わせながら自分の両肩を抱いてペタペタと歩く。
洞穴の奥。そこに住む人物を少女は知っている。
「ずいぶんと、姿が変わったものだな」
また、洞穴に住む者も、少女のことを知っていた。
「いつもの調子はどこへ行った。森の主と名乗る者よ」
少女は、自惚れた白蛇だった。
「……っう……ぁあぅ……ッ」
「──繰り返しても学ばないやつらだな……哀れな者よ」