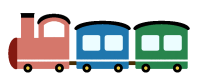ミーちゃんと呼ばれる少女の母親に旅人は昼食を招かれ、その子の家で昼食を共にすることになった。
「旅人さん、ミーちゃんと遊んでくれてありがとうね」
「違うよおかあさん。私が遊んであげたんだよ」
一つのテーブルを三人で囲み、その子──仮にミーと呼んでおこう──が片手にフォークを握ったまま母親に言う。
「そうなの?」
「違うよおかあさん。こいつが遊んでほしいってごねるから付き合ってあげたんだよ」
「ごねてないッ! 嘘っぱち! あとおかあさんは私のおかあさんなの! 勝手にそう呼んじゃダメなんだから!」
「あ? ダメ?」
「ダメ!」
ミーは皿にある目玉焼きをフォークでグサッと刺し、乱暴にナイフで切って口の中に入れた。旅人はニヒヒと笑っている。
「私はどっちでもいいけどね。子供が二人できたみたいで楽しいし」
「おかあさん!」
「ミーちゃんは嬉しくないの? お兄ちゃんができて」
〝お兄ちゃん〟という単語にミーは一瞬体をびくりと震わせた。ゆっくりと顔を横に動かし、隣の席の旅人を見る。
「お、おにいちゃん……」
小さく呟き、顔をほんの少し桜のようなピンクに染めた。一緒に遊んで気を許せるようにでもなったのか、意外とまんざらでもないようだ。
「ははっ、妹か。いいかもしれないな」
「バ、バカ! 私絶対イヤ!」
そう言い捨て、ミーは顔をまた一段と紅潮させて目玉焼きを食べる。
「そうだ。旅人さんがよければここに住むといいわ」
「オレがここに?」
「私の養子になってもいいのよ? 旅なんてやめて、ここに住んじゃいなさい。きっと楽しいわ」
「…………」
旅人は母親を見たあと、ミーを見て、そのあと自分に出された目玉焼きを見た。
「……変わった……目玉焼きだね」
「え? えぇ、まあ……」
いきなり話題を変えられ、不思議と思いながらも母親は返した。
「ミーちゃんの好物なの」
その目玉焼きは、〝目玉〟と言うべき黄身が無く、白身だけをただ焼いたもの──言わば白目焼きだった。
「お気に召さない?」
「イヤなら食べなくていいよ」
白身だけの目玉焼きがイヤと思ったのか、ミーは少し不機嫌そうに目を逸らす。
「……いいや。……オレも、黄身が入った状態は好きじゃないんだ……」
「え」
「好きだよ、この方が」
そう言って旅人は白身を食べる。
「……珍しいね」
「そうか? ……いや、そうだな。オレが住んでたとこも、オレんち以外目玉付きだった気がする」
「変じゃないよね? 目玉無しって……」
周りと違うことに劣等感を抱いていたのか、ミーは不安そうな目をして旅人を見つめる。旅人は困るでも馬鹿にするでもなく、ただ微笑んだ。
「好き嫌いが人と違って何が悪いんだよ。誰が変って決めた? 自分が変じゃないって思えば、それは変じゃない。自分の好みを無理に周りと合わせなくていいよ」
「そう、だよね……! いいよね! 私は私で!」
「ああ。それがおまえの意思ならな」
それを聞いてミーは嬉しそうににこっと笑った。
「旅人さん、話を戻すけどここに住まない?」
「私もおにいちゃんなら……住んでいいよ」
旅人のことが気に入ったのか、ミーもここに住むことを勧める。
旅人は目を瞑ってふぅと息をついた。
「そうだな……ここにいれば、きっと楽しいだろうな」
「じゃあ──」
「でも住めないよ。オレはもうこの時間に入れない」
眉を八の字にさせ、切なそうに旅人は笑う。それにしては微塵の迷いもないきっぱりとした答えだった。
母親は悲しげに顔を下げたが、すぐに笑みを顔に表した。
「旅人さんが決めたことなら、仕方ないわ」
「……ありがと」
それだけ言うと、旅人はもう出て行こうと椅子から腰を上げて机にもたれ掛けておいた竹串を手に持ち、外への扉に手をかける。
「おにいちゃん!」
後ろから声がし、頭だけ振り返った。
「本当は嫌いなんでしょ! 私も、この家も……この目玉焼きだって……本当は嫌いなんでしょ! だから出ていくんだ!」
椅子から降りていたミーは、両手に拳を作って怒鳴る。それに対して旅人はやんわりと穏やかな顔をしていた。切なげな面影を残して。
「好きだよ」
「だったら行かなくたっていいじゃん! ここに住んだっていいじゃん!」
ミーは憤慨したまま駄々をこねる。その姿に旅人は遠いものを見るように目を細めた。出会ったばかりのはずなのに、最初は見知らぬ自分に敵意を示していたはずなのに、いつの間に懐かれてしまったのだろう。目の前の子供はひどく喜怒哀楽が激しい。いい意味で言えば、自分の感情に素直で純粋な子だ。拗ねることは多いけれど、そういう子だったのだ。
今にも泣きそうな遠い相手は、手を伸ばせば、少し歩けば、届く距離にいる。ほんの少しの距離だった。旅人はゆっくりと近づいて、そっと抱き寄せた。
「……わがままだな、お前は」
「急になによぅ……」
「わがままで、思いどおりにならないとすぐ怒るし泣く」
「それが私だもん」
「そうだな。それがお前だ。だから、お前はお前でいてくれ。母親が好き。母親がつけてくれた自分の名前も好き。ずっと……ずっと、そういてほしいんだ……」
旅人はミーの肩に両手を置き、しっかりと顔を見る。ミーも涙目になりながらも、しっかりと旅人の顔を見つめた。
「オレがここにいる必要はないんだ。お前がいてくれればいい」
「でも……ここにいれば楽しいよ? 幸せだよ?」
「楽しいことはお前にやる。幸せもお前にやる。オレは自力で面白いことを探すからいい」
「本当にいいの?」
「ああ」
「……そう」
静かな声色なのに、やはり迷う素振りもないきっぱりとした言葉に、旅人の揺らぐことのない意思が詰まっていた。諦めたようにぽつりと呟いたミーは、けれど彼女も母親同様にっこりと笑って見せた。旅人の決意を尊重し、邪魔にならないよう。
「それでいい……」
旅人も笑って返し手を離すと、ミーは母親の元へタッタッと戻っていった。母親も椅子から立ち上がってミーを抱き寄せる。二人の寄り添う姿は幸せそうな親子そのもので、旅人の目には至極遠い存在に見えて仕方なかった。それと同時に、不可侵な空間でもあると。どれだけ望んでも望まれても、そこに旅人の居場所は無い。干渉する余地だってないことを、旅人自身が自覚していた。
「いってらっしゃい」
我が子に言うかのようなやさしい声色で母親は微笑みながら旅人を見送る。すると二人の顔は乾いた泥のようにひびが入り、次第にボロボロと崩れていった。この家もギシギシと軋む音を立てながら崩れ始め、壁も、天井も、机も、そして床も、この空間のもの全てが崩れていく。
旅人は崩れ落ちていく現象に気を留めず歩き、扉に手をかけたところで二人へと顔を向け、ニッと笑顔を繕った。
「──いってきます」
ガチャ、パタン。
外へ足を踏み出すと、差し込んだ太陽の光が眩しくて目を瞑る。ゆっくりと目を開け旅人が今いたはずの家へ振り返ってみると、その家はすでに崩壊しきりただの瓦礫の山と化していた。見渡せば、のどかな村なんてどこにも無く、ぽつぽつとあった家々も瓦礫の山になっている。駆ける子供も、洗濯する主婦も、薪を折る男も、散歩する老人も、誰もいない。まるで最初から誰もいなかったように。
旅人は再度、今自分が入っていた家の中に目を向けた。
「幸せはお前にやるよ。名前もお前に譲る。だから大事にしろよな──」
「ミコト」
そう言い残して、旅人は最初に会った男の元へと行く。
そこもやはり瓦礫の山で、瓦礫の頂上に男は座って楽しそうに笑っていた。男の隣にはきっと、男の言う美人な妻がいるのだろう。
「……それがあんたの幸せなんだな」
旅人はそれを見届けた後、その家のさらに向こう側へ歩いた。
緩い丘を下ってみると、広い更地に複数の墓石が立てられていた。墓石は汚く、長年掃除されていないのがわかる。
それだけ確認すると旅人は男をおいて村を出た。橋は石造りだったため劣化していなかったが、小川は存在しておらず、水は流れずに干上がっていた。
春の陽気は夢の色
その夢をあなたは幸せと言う
暖かな夢の中はかつての温もりを思い出す
春の陽気は夢の色
その夢をあなたは幸せと言うけれど、
幸せのない私は何の夢を見るの?
「オレにとっての幸せは、ずっと昔に失ったよ」
ああ、
あのときはきっと
私も幸せでした