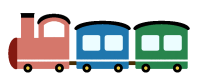*
「そうして私はここに閉じ込められた。私を恐怖した哀れな人間の手によって」
「……ルコンさんと親しかった人は、どうなったの……?」
「ああ、バケモノを匿った裏切り者として酷い目に遭っていたわ。仕方ないことよ。元々変わり者としてよく思われていなかったしね」
「……仕方ない、で済むんですね」
「ええ。私があの人間に手を貸したばかりに酷い目に遭った。だから私のせいになるとでも?」
「…………」
「ふっ、冗談じゃない。あいつが変な好奇心さえ持たなければこうはならなかった。私だってこうはなっていない。自業自得。そう、自業自得だ……」
その後ぽつりと何か呟いたように聞こえたが、■■は気に留めなかった。
「……あれ。じゃあなんで今も──」
「私の話はもう終わり。さあ、とっととそれを食べなさい」
話の不可解な点に気づいた■■だったが、まるで話すのを拒むように切り上げられてしまい言及することができなかった。仕方なく手に持っていた土を見下ろし、渋々と口にした。
「……まずい」
■■はルコンと洞穴で日々を過ごした。何日も、何日も、繰り返し土を食べ、寝て、それ以外にすることはなくぼーっとする。時折ルコンが一言二言声をかけてくるが、それ以外に■■が声を返すことも、自ら話しかけることもなかった。ぼうっとふわついた頭をしたまま心の中では自問自答を繰り返し、だんだんと意思が薄れていく。
この姿になる前の自分。この姿にされて『人間』として過ごした偽りの自分。本当ならいないし、もっと前に死んでいたはずだった。──それならここにいるのは誰なんだろう。
そう思うのが日常になり、いつしか■■の目には光が無くなった。
「…………」
そして言葉を発することさえなくなった。どこを見ているのかわからない虚ろな目。
「たまには洞穴から出たらどう?」
「…………」
ルコンからそう言われても、■■は座り込んだまま俯くだけだった。
「……ふぅ。つまらなくなったわね」
そんな言葉を浴びせられても、■■は気にすることなく無表情で土を食べた。
あっという間に一ヶ月が過ぎ、絶食期に入った。
空腹との闘い。土を食べていた頃は腹が満たされなくても口に何か入れるだけで凌げた。ルコンの言うとおり、たとえ土でも食べられただけでましだったのだと痛感する。
苦しい。
なんでこんな目に遭っているのだろう。時折とてつもない悲しみと苦しみに蝕まれる。
なりたくてなったわけじゃない。好きでこんな姿になったわけじゃない。それならなぜこんなことになっているのだろう。
ふわついた意識のはっきりしない頭の中、脳裏に浮かんだのはいつだったか過ごしていた平和な日常。そして絶えない笑顔。
あんなに幸せだったのに。あんなに楽しかったのに。あのまま日々が過ぎるだけでよかったのに。──今ではもう、まるで何も知らない自分を見下し嘲笑うかのように思えて、幸せがとても憎たらしくなった。
自分は被害者だ。悪いのはあの家族。
そんな問答を繰り返し幾日。ある日■■が眠りから覚めると、ぐらりと視界が歪んだ。ひどく意識が朦朧とする。眼鏡がなくても物が見えるように視力を治してもらったというのに、周りは輪郭や境界がはっきりとしない景色。まるで記憶を失くして目を覚ましたあの日のようだ。違うのは、あの時は周りが真っ白だったことに対して、ここは真っ暗だということ。
なんとなく立ち上がるもふらふらとする。少し動けばこの朦朧とする世界がくっきり見えるだろう、そんな気がしたのだが直らなかった。長いこと最小限動かず洞穴の中で過ごしていたせいで、自分の体を動かす感覚さえ朧気になってしまった。夢の中と錯覚するほど視界も感覚もなんだか鈍い。立ち上がったり周りを見ることで目に映るものも視点が変わり動くが、それら全てがいくつもの残像を残して映っているように見えた。
気持ち悪い。まるで濁った空気を吸っているかのような吐き気に襲われる。この空気から逃げるように■■は外へ向かって壁を伝いながらゆっくり歩き出した。
洞穴から出ると、久しぶりの陽の光が差し込んできた。この一帯だけ木が捌けているとはいえ森の中という薄暗さがあるのに、しばらく洞穴で過ごしてきた■■にはあまりに眩しくて、手を額の上に掲げ顔を下げた。まだ視界が薄れている。そもそも自分は生きているのだろうか? そう思えるほどに感覚は悪いままだった。
「…………」
なんとなく口を開くが、声が出ない。
塞ぎ込んでは嫌な思い出しか頭を巡らず、鬱憤が溜まった暗い気分は外に出ても晴れることはなかった。憎たらしい幸せのかわりに眩しい太陽が■■を睨む。太陽すらも憎たらしい。
おとなしく洞穴に戻ろう、そう足を退いたその時だった。
「お兄ちゃん!」
その言葉が鋭く■■の耳を貫いた。
『お兄ちゃん』
懐かしい声。脳裏にはその声の主の明るい笑顔がいくつも浮かんだ。あの頃はその笑顔を見るとなぜだか自分も安心できて、幸せになれた。
そう、幸せに。
「……んで……こんな、ところに……っ」
だが今となってはただの苦痛にすぎない。
国にいるはずなのになぜ森の中に。なぜ自分の前に。そんな当たり前の疑問は今の■■には浮かぶ余地がなかった。
胸が熱く苦しい。息切れがする。思い出すだけで自分を苦しめ続けたモノが今目の前にいる。
「……ぜェっ、……はァ……」
苦しい。くるしい。クルシイ。
──ナンデ、コンナ目ニ……
「お兄ちゃん大丈夫?! 具合悪いの? ずっと捜して──」
「くるな゛ぁ……ッ!!」
苦しい胸をギュッと掴み、近寄ってくるいつの日か妹と呼んでいた相手を■■は睨んだ。
「おにい、ちゃん……? どうしたの……」
一瞬びくりと体を震わせ動きを止めてしまった□□だが、またすぐ心配そうに■■へ足を運ぶ。■■の苦しみの原因がまさか自分自身だということも知らずに。そうしている間にも■■は苦しげに息切れを起こす。頭の中ではぐわんぐわんと警鐘が鳴っているようだった。そんなままならない頭でも思考は巡り続ける。
この人間はまだ自分のことを兄だと思っているのか。本当は違うくせに。白々しく、まだ自分を騙して見下して心の中では蔑んで、人間じゃない自分を飼い続けるのか。見上げるその目が憎たらしい。何も知らないフリなんて、自分をどれほど愚弄し続けるつもりなんだ。
そして、とうとう■■の中で何かが切れた。
「ぜェ、……うる、さい……っ、うるさい……やめろ……はァ、はァっ……ぜんぶ……ぜんぶっ、おまえのせいだあああっ!!!」
バシンッ!
怒号と共に張り裂ける音が鳴り響いた。気づけば■■は右腕を伸ばしており、その先には□□が倒れていた。■■は自分でも無意識のうちに□□を張り倒してしまったことを理解する。
自分の理性をギリギリで保っていた一線。それを越えてしまった■■の心は、いまにも壊れそうなほど不安定だった。
「ハアッ、ハァッ……、ち、がう、ぼくじゃない……じぶんのせいじゃ、ない……じぶんは……、なにもわるくない……じぶんは……じぶんは……ぅぁあああああッ!!」
平和なんて……幸せなんて……大嫌いだ…………。
「おまえが……おまえたちが、いるから……いけないんだ!」
自分が□□に手をあげたことに罪悪感なんて抱かない。むしろ殺意すら湧いていた。
自分は被害者だ。自分をこんな目に遭わせた人間を赦さない。自分は何一つ悪くない。
ひとりでいたかったのに……。
いつまでも頭の中で巡り続ける幸せ。染み付いた記憶を薙ぎ払いたいのにしつこくこびりついて離れない。こんな思いはもう嫌だ。もうたくさんだ。
笑顔なんて見たくない……! 見たくない! 笑顔を見せるな──ッ!!
「アアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアア!!!!!」
凶器のように鋭く伸びた爪を振り上げ、□□に向かってかざした。
これできっと、楽になれるんだ……──