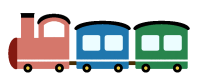「今日からこの特別学級で一緒に勉強することになった■■君と妹の□□ちゃんです。■■君は事故に遭った影響で記憶に支障があり学力が落ちてしまったためにこの学級に来ました。わからないことが多いと思うので、困っていたらみんな助けてあげてくださいね」
登校初日。今年特別学級に入学する生徒は僕と□□の二人だけで、この学級には十数人の生徒がいる。先生が僕たちを紹介すると、席についている子たちに拍手を送られた。
僕らの席は教室の後ろだった。窓脇に並んだ日当たりのいい座席で、僕と□□は隣り合って座る。ちらりと窓から外を見ると、小鳥が数羽横切っていくのが見えた。今日は晴れてていい天気だ。
顔を前に戻すと、前の席の長い茶髪をした女の子が振り向いて僕らをじっと見ていた。僕と□□を交互に眺めると、ふいににこっと笑う。
「私はユリ。七歳よ。足が悪くてこの学級なの。あなたたちは? 歳はいくつ?」
「えっと、僕は十歳だよ」
「私は六歳!」
「□□ちゃんとは歳が近いね。二人ともよろしく!」
ユリはにこやかに笑って□□、僕の順に手を握って明るく接してくれた。足が悪い、と言うためユリの足元を見てみたが、ちゃんと二本の足がついている。ズボン越しだし、見た目だけじゃわからないのだろうか。僕の記憶喪失だって見た目じゃわからないし。僕は目線を戻した。
「私には普通の学級にお兄ちゃんがいるの。トモ君って言って■■君と同じ十歳よ。また紹介してあげるね! ■■君と仲良くなれるはずだから」
「お兄ちゃん? 僕と同じ……」
「そうね。私のお兄ちゃん!」
初めて□□以外の子供と話して少し緊張してしまったが、明るく笑うユリのおかげで肩の力がすっと抜けた。学校に通うことに不安はあったが、いらぬ心配だったな。ユリのお兄ちゃんという人に会うのもなんだか楽しみだ。
特別学級には僕のような十歳の、世間で言う五年生の子もいれば、□□のように本来一年生であろう子までいる。そのため、この学級の授業能率はけっこう悪い。僕みたいに学力を失っていればまだいいけど、ユリのように身体に異常があるだけで学力に問題ない子だっているのだ。そのため各々で勉強する内容が違い、その子の学力に合った教材を使って各自勉強したり、先生から課題の用紙をもらってそれを解いたりするようだ。わからないところは先生が回ってその都度受け答えをしている。同じくらいの学力同士の子は机をくっつけて一緒に勉強に取り組んでいたり、年上の子が勉強を教えたりもするらしい。
僕と□□とユリは三人同じくらいの学力だったから机をくっつけた。僕だけ場違いな気がしなくもないが、学力が下がっているのだ。仕方ない。僕も頑張って勉強して学力が上がれば教える立場になれるのかな。
そしてこの学級では一般学級にある体育という授業は無い。かわりに遊戯のような、軽く遊ぶ程度の体を動かす時間がある。ユリのように足に障害を持った子がいるし、人並みに体を動かすのが難しい子がいるのだろう。
今日はボールを蹴る遊びをした。円を描くように並んで立ち、ボールを蹴って誰かにパスをする。それだけの軽い遊びだ。
「それでは□□ちゃんからやってみましょうか」
「はーい」
□□は元気よく返事をし、先生からボールを受け取って足元に置いた。先生は生徒と一緒に輪の中に入り、□□と変わらない歳の男の子の手を握っていた。
「じゃあけるよー」
ポンと音を発したボールは軽い弧を描いて正面の子に向かう。その子がボールを蹴ると軌道が横にずれ、ユリの足に当たった。
ポスッ。
「ごめん! 大丈夫!?」
「大丈夫大丈夫!」
ユリはVサインを出してボールを蹴り始めた。足を気にしている様子はなさそうだ。
「?」
今日の授業は午前だけだった。終わればみんな下校をする。僕と□□もすぐ帰る予定だったけど、ユリがトモを紹介すると張り切っていたため校門の前でトモという子が来るのを待った。
「ユリー!」
しばらくして茶色の短髪をした僕より少し背の低い男の子が手を振りながら走り近づいてくるのに気づいた。それを見たユリも手を振り返す。
「トモ君ー!」
この子がユリの兄のトモらしい。
「ユリ、こいつらは?」
「私の友達! ■■君と、□□ちゃんだよ。二人とも私と同じ特別学級なの。あのね! ■■君はトモ君と同い年だから仲良くなれるかなーって思って二人に待ってもらってたの!」
「ほぉーそっか。えぇと? オレはトモノリ。ユリとか友達にはトモって呼ばれてる。■■と□□よろしくな」
そう言ってトモ……ではなくてトモノリはにっと笑って手を差し出した。
「あ、よ、よろしく」
僕はその手を取ると、トモノリはブンブンと大きく手を振った。その次に□□にも。
そして僕らは途中まで一緒に帰ることになった。
「へぇ、■■は事故で学力が落ちちまったのか。しかも記憶まで」
「まあ、ね」
「事故ってどんなの? 見た目は傷とか無ぇよな。頭打ったとか、骨折したとか、そういうんは?」
「え……、僕も詳しく知らない……憶えてないし……。記憶喪失による知識の欠落? と、視力の低下くらい……。□□は知ってる?」
「ううん。ただの事故だよ。お母さんそうとしか言ってないし、私もわかんない」
「だよね……」
「ふーん、そっか……」
トモノリは不思議そうな顔を空に向けて、頭に腕を組んだ。いったいどういう意味だろう。たしかに外傷というものは無いが、知らないだけでもう治っているのかもしれない。少なくとも僕が目を覚ました時は、体のどこかが痛いとかそういうのはなかった。それはおかしいのだろうか。
「ああ、ごめんごめん。ユリとは違うんだなって思っただけ。んな深刻な顔すんなって」
「あのねあのねっ、私も前に事故に遭ってね、両足義足なの。だから■■君もどこか切ったのかなーって、──トモ君はそう思ったんじゃない?」
「ははっ、まーそんなとこ。怪我の種類も事故によるわな」
「ぎそく?」
「うんっ。これ作り物の足なんだよ。すごいでしょ!」
ユリはそう言いながら一歩前に出てくるりと回った。特に問題なく動いてみせるが、たしかによく見ると、教室で見た時はわからなかったが膝から下のズボンの膨らみが変だった。皮膚や肉といった柔らかいものを覆っているわけではなく、無機質な固い棒状のものがズボンの下に隠れている。
「見た目がこわいからちょっと見せられないけどね」
膝下だけ木製の人形のような足が付いているのかなと想像してみた。なるほど。何も知らずに見ていたら驚いていたかもしれない。でもその足を自在に動かせるのはすごいと思う。
そしてふと気づく。
「あ。だから音が違ったんだ……」
「音?」
「ほら、ボールが足に当たった時。なんか音が違うなって思ってたんだ。だけど誰も気にしてないし、ユリも平気みたいだったから、気のせい、なのか、な、って……」
遊戯のことを思い出して話してみるが、次第に三人から集まっていく視線に耐えられなくなり徐々に言葉が片言になってしまった。無言の視線という圧がなんだかこわい。
「え、っと……」
「すごい! 音で気づいてたの!? 当たったのゴムボールだよ?」
まずいこと言ってしまったのかなと口籠もってしまったが、返ってきたのは感心する声と大きく輝かせた目で、思いもよらなかった反応に少し怯んでしまう。
「う、うん、でもちょっと音が違ったから……。あっいや、ほんのちょっとね! 少し!」
「私も同じに聞こえたよ!」
ユリだけでなく、□□まで僕を見つめはじめる。そんなすごいことをしたつもりはないのに……なんだか恥ずかしいな。
「■■ってすっげー耳してんな! うらやましーオレ聴力低いから分けてほしいぜ!」
「ぅわっ!」
今度はトモノリがにやにやと笑いながら僕の肩に腕を回してきた。なんとも距離が近い。この兄妹は揃って明るい性格だ。しかし僕は初めてのことでトモノリの接し方に戸惑ってしまう。悪気があるわけじゃないし、むしろこういう剽軽さに親しみやすさがあるのかもしれないが、僕はまだ慣れないな。
そんなことを思っていると、トモノリは突然真剣な表情を見せた。
「両足義足のユリだが、仲良くしてくれるか?」
ついさっきまでとはあまりに真逆な顔で、僕は思わずごくりと唾を飲んだ。まっすぐ見つめるその目に冗談なんてない。
でもきっと、それだけユリのことを思っているんだろう。僕だって記憶が無かったり知識があまりなかったりする。ユリの持つ障害とはちょっと違うけど、障害という意味では同じだ。普通の子供と違うという障害を持ったまま学校に通うことに対して、他の子と仲良くできるのか、上手くやっていけるだろうかという不安があった。自分自身が緊張しているのもあるけど、相手からどう思われるのか、少し怖かった。きっとそれと同じなんだ。トモノリは、ユリの作り物の足に対して僕が変に思ったのかもしれないと、心配したんだ。
僕のことを気にせず初めて声をかけてくれたのがユリなのにね。
「もちろんだよ」
そう返事すると、トモノリは安心したのかまたにっと笑って僕の頭に拳をぐりぐりと押さえつけた。
「約束だぞー!」
「いだだ! いだいよ!」
「あぁ! お兄ちゃんをいじめちゃダメー!」
「トモ君トモ君、■■君がまた記憶喪失になっちゃうよー」
やっぱり、こういう接し方はまだ慣れないな。
「じゃあねー□□ちゃん■■君ー! また明日学校でねー」
「また一緒に帰ろうなー」
「またねーユリちゃんトモ君」
分かれ道に差しかかり、僕を除いた三人は元気にそう言って手を振りながら別れを交わす。そんな中僕だけは、なぜかそれが言えないでいた。自分から声を出すのにまだ慣れていないというのか、同年代の子と一緒になって挨拶を交わすという行為に怯み躊躇ってしまう。僕がそこに混ざっていいものかと。
そうこうしている内に、二人はどんどん先を行き離れていく。今さら言っても遅いし、声も届かないかも。手が胸の高さで止まったまま上がらない。
明日、頑張ってみようかな……。
「■■ー! オレたちはもう友達なんだから、オレのことはトモって呼んでくれー!」
「あ……」
察してくれたのかどうなのか、だいぶ遠くなったトモノリからそんな声が聞こえた。後ろ歩きしながら両手をブンブン大きく広げ振っている姿が見える。
僕は勇気を出してゆっくり手を上げ、そしてなるべく大きな声を出しながら手を振った。
「また明日ー! ユリー! トモー!」
「おーう!」
トモがにやりと笑ったのが見えた気がする。明日の学校もなんだか楽しみだ。
「ただいま」
「ただいまー!」
家に帰るとお母さんが玄関に来て「おかえり」とやさしい笑顔で迎えてくれた。
「学校はどうでした?」
「うん、友達ができたよ。授業も楽しかったかな」
「そう! よかったです。□□ちゃんは?」
「ボール蹴ったよ! 楽しかった!」
「そうですか。二人とも楽しく過ごせたようでよかったです」
お母さんはにっこりと微笑んで手を合わせた。
昼間はお母さんと□□と一緒に庭で遊び、夜になったらお父さんが帰ってくる。そして一つのテーブルを囲んで四人で夕飯を食べる。今日のことを話して笑い合い、歯磨きを済ませたら□□とお風呂に入って二階に上がって自分の部屋に行く。僕と□□は同じ部屋で、二つ並んだベッドに潜った。
「お兄ちゃん、学校楽しかったね」
「そうだね」
初めて学校に行った興奮がまだ冷めないのか、声をひそめながら□□が語る。
「明日は何をするのかな」
「うーんなんだろうね」
「またボールけったり遊びたいなー」
「お昼お母さんとも遊んだのに?」
「それはそれ、これはこれー」
「あはは。僕はもっと勉強したいな」
「お兄ちゃんまじめだー」
「まじめだよー。忘れたこと、ちゃんと知りたいし。□□に色々教えれるようにもなりたいから」
「色々教えてくれるの?」
「そうなりたいなーって。まだ難しいかもしれないけど」
「お兄ちゃんなら大丈夫だよー。私もついてるしっ!」
「ふふっ、心強いな。ありがとう。じゃあそろそろ寝よっか。朝起きれなくなっちゃう」
「うん。おやすみー」
「おやすみ」
楽しかった余韻に浸りながら目を瞑った。
初めての学校。初めての友達。ふざけてトモが僕に手を出したりもしたな。□□は本気で心配そうに声を上げて、ユリはトモのように冗談っぽく笑って。
思い返しても、いい一日だった。こんな時間が増えるなら、記憶喪失になってよかったかもと、思ってしまう。
……でも何か、違うような……。たしかに楽しかったのに……。
前の自分がどう過ごしていたのかわからなくて、今いる自分が本当に自分なのかふと実感が湧かなくなる。瞼の裏に蘇る今日のことすら、だんだんかすれて見えてしまう。色はあるのに……なぜか世界が灰色に感じる。まるで夢の中、のようで……。
……なんでだろう………。僕はここにいるのに……。いるはずなのに……。
「お兄ちゃん」
「……なに?」
「手、にぎる?」
「……届かないよ」
ガサゴソと音がしたかと思うと、□□がこっちのベッドに入ってきた。
「届くよ」
暗いし、眼鏡を外した僕の目にはよく見えないが、きっと今□□は自信満々の笑みでも向けているのだろう。それを想像して、僕はくすりと笑う。握られた手を僕も握り返した。
「おやすみ」
「おやすみー」
……温かい。
病院で目を覚ました時も、不安だった僕を安心づけてくれたのは□□だった。手を握る感触はちゃんとある。僕はここにいる。実感がある。
──大丈夫。僕は孤独じゃない。