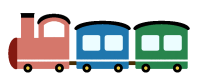ふいにカジハはその場からふらりと去り、お茶を持ってきた台所に入ったかと思うと、よく研がれた包丁を手に持って戻ってきた。
キイィィィン──
何度も何度も鳴るこの音に意識を失いそうになるが、今意識を手放したらそれは死を意味するとノンは即座に判断した。否、判断ではない。条件反射だ。
「──ッ!」
キイィィィン──
カキンッ!
二つの音が重なり合った。
先ほどから鳴り響く音。そして、カジハが振りかざした包丁とノンが瞬時に腰から引き抜いたナイフの擦れ合う音。
「聴こえますか? あの偉大な音が」
「……偉大な音? 何のこと、ですか……っ」
「とぼけても無駄ですわ。聴こえているのでしょう? 頭に響く聖なる音が」
〝聖なる〟なんて何を言っているのかさっぱりだったが、〝音〟や〝頭に響く〟という言葉でノンは理解する。
「……この音、ですか。さっきから耳障りで、仕方ありませんよ」
「そうですか。聴こえているのですね。なら──死んでください!」
「ンっ──」
カジハは満面の笑みで包丁を両手で握ってノンの顔面に向かって振りかざしたが、ノンはナイフでその包丁の刃を斬り落とした。落ちた刃先が土の床にザッと突き刺さる。
カジハは自分の持つ刃先の無くなった包丁を一瞥すると、動揺するわけでもなく首を傾げてノンに言った。
「なんてことをなさるのです? これではあなたたちを殺すことができないではありませんか」
「そうですね……、シキを守れて、よかったです……」
会話がまるで噛み合っていないことを気にもせず、カジハは使えない包丁を握ったままノンに話す。あくまで対等に。さも自然に。ノンも同様に言葉を交わそうとするが、やはり劈く音のせいで途中途中言葉が詰まった。
「そのナイフを私にください。見たところ変わっていますが、切れ味は良さそうです。それを使ってあなたたちを殺してさしあげますわ」
「お断り、します。これは自分専用です。あなたには扱えない。死ぬつもりも、ありま、せん……っ」
「困りましたね。これでは殺せない。我が主に認めてもらえないではありませんか」
キイィィィン──
異常な会話の中でも響く音に頭がくらくらする。目に映る世界は揺れ、足の踏ん張りもままならない。それに対してカジハは平然としている。音に慣れているのか、それともカジハが意図的に起こしているものなのか。もしくは音の影響でカジハが豹変したのだろうか。ノンには相変わらず思考を巡らす余地すら与えられなかった。
「……ッ……なぜ自分たちを殺そうとするんですか? さっきと人が変わったようですね」
「変わっていませんよ。ただあなた方に我が主の声が聞こえているようなので殺させてもらいます。聞こえないのならそのまま帰してもよかったのですが……仕方ありませんよね」
「……そうでしたね。たしかにあなたは最初からそんな目をしていました。ですが、音を聞いただけで殺すなんて、理由がまだわかりません。自分に言わせれば、仕方ないわけないですよ」
ノンとシキが最初カジハと会った時、彼女はその時からすでに目の色が歪んでいた。生きているのか死んでいるのかもわからないような曖昧な目の色だ。それなのにノンと違ってよく笑い、表情がある。だが実際には、彼女に表情はおろか、感情すら無かったのだ。彼女の顔には偽りの表情しか映らず、心にも表情が無い。目の奥に光が灯されていなかった。まるで何かに取り憑かれているかのように。
「そうですね。それではこういうのはどうでしょう? 私はあなたたちを殺さないでさしあげます。そのかわりに、あなた方の耳に届いているその音を私にも聴かせてください」
カジハがそう交渉してくると、ノンはあることに気づく。
「カジハさん……あなたはこの音が聴こえていないんですか……?」
『聴かせてほしい』と言うからには、本人には聴こえていないのだ。今もなお響いている、
キイィィィン──
この音が。
「ええ、そうです。聴こえない、というより……聴こえなくなった、と言った方が正しいですけど」
そう言ってカジハはにっこりと笑った。
「……詳しくはうかがいません。あなたの言うとおりにします」
「あら、話がわかってよかったですわ!」
カジハは喜んで包丁の柄を挟んで手を合わせると、包丁を机の上に置き、さっきまでカジハが座っていたソファーの裏にある土でできた棚の方に行き、棚上に置かれてあった箱を下ろして持ってきた。
その箱は土でできておらず、高価そうな装飾を準えた木製のものだった。外見は漆黒に染められ、唐草のような模様が描かれている。不気味と捉えられれば神秘的とも捉えられる箱だ。
カジハが箱を開けると、中には丁重に保管された横笛が入っていた。その笛も箱と同じように、黒い外見に唐草模様が施されている。
キイィ……ィ……
(……音が、止んだ……?)
箱から横笛の姿が露わになると、今まで響いていた音が不思議と止まった。
「これがあなた方の耳に届いている音の正体。我が主です。なんとも美しく高貴なお姿でしょう?」
たしかに綺麗で美しい。だがここまで美しくあると、逆に気味が悪くも感じえた。
カジハは両手でそっと笛を手に取り、丁重にノンの前に差し出した。
「何が聴こえます?」
期待する眼差しを向けられるが、あの貫くような音はもうしない。本当にこの笛があの音の発信源だったのかと疑うほど、静かにカジハの手の中に収まっている。
「聴こえません。この笛を目にしてから音が止みました」
「……え。聴こえ、ない……?」
「はい。今はもう何も聴こえません」
それを聞いたカジハは目を大きく開き、呆然と焦点の合わない目をしながらも持っていた笛を箱の中にそっと入れ、次に包丁を握った。
「なら、あなた方に用はありません。死んでもらいます」
そうしてにたぁと不気味に笑った。話の通じない相手を前にここにいても無駄だろう。ノンはゆっくりとナイフを腰に差し、気絶したままのシキの体を抱き寄せて逃げる体勢を整えた。
「たとえ刃が折れていても、深く刺せばきっと殺すことができますわよね」
うふふと笑いながらカジハは包丁を構える。たしかに刃は折れているが、折れた部分の断面はやや鋭く、深く刺されたらただでは済まないだろう。
ノンは出口までの距離を横目で辿って測り、カジハがこちらに向けて走ると同時に逃げれば出られると目測すると、まばたきせずにカジハを見つめた。
「さようなら、旅人さん──」
足に力を込め、いざ踏み出そうとしたその時。
《我が言葉が聴こえるのなら、主は正直な者であろう。しかし、我が意思も無く聴こえぬものなら、主に真も誠も語れまい》
カジハが駆け出した瞬間、そんな声が聞こえた。それは、ノンが最初に聞いた低い声だった。だが今のこの声は気持ち悪くなく、単に低い声だ。それも、あの奇妙な黒い唐草模様の笛から聞こえた。