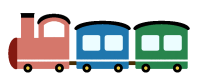「ずっと一緒だよ、大丈夫。苦しまなくていいんだよ」
……普通は逃げるはずだろう?
傷つけて、恐がらせて、今でも殺しそうになったのに。それでもなぜその子は笑っているのだろう。なぜ自分に抱きついているのだろう。わからない。わからない……。
わからないけど、自然と涙がこぼれた。
「……ぁ、……」
ぼやけた世界がようやくくっきりと見えるようになった。これは夢じゃない。現実だ。
なんて残酷な世界だろう。
自分の理性を取り戻し、■■はすとんと膝を落とした。
「ぅっ、ぁ……。もう、いいよ……ひっぐ……ぼくは、いないんだ……おねがいだ……じぶんをひとりにさせて……。さもないと……ほんとうにきみを、ころしちゃう……。はやくじぶんから、はなれて……うっ……」
「そんな……。ようやく会えたのに! そんなこと言わないでよ! 一人になんかしないよ……。ねえ、一緒に帰ろう……?」
その言葉にまた■■は理性を失いそうになった。『一緒に帰ろう』だなんて、なぜそんなことが言えるのだろう。歯をキリリと食いしばり、自我を保った。
「うそはもういらない……。はやくかえるんだ……かえれッ!」
「お兄ちゃん……」
「やめろ!」
「あらあらまあまあ、これはまたずいぶんと酷い姿になったわね」
声のした洞穴の口を見ると、そこには鎖で繋がれているはずのルコンがいた。足元の鎖は見当たらない。
「誰……?」
「知らないのも当然ね。私はルコン。……ふふ。あなたは昔よりまともな生活を過ごしてきたみたいね」
「?」
「まあそんなことはいい。問題はぼうや。自分の姿を見なさい」
言われるがままに■■は自分の身体を見た。痩せた体つきは当然だったが、それにしては骨格がはっきりわかるほど細く伸びた手足に、凶器のように鋭くなった爪。自分で確認はできないが、目元は隈のような模様が三重に張り、頬にもその模様が二重浮かんでいた。瞳孔は縦長に開いており、まるで獣のようだった。
「ぁ……はァ……」
「お前の中に残る元の野生の血は、お前の興奮の昂りに反応する。その血を抜け。冷静になれ」
ルコンはそう言って手に持っていたナイフを■■の足下に投げた。
■■はナイフを拾い、ルコンを見、□□を見た。
「さあ」
ルコンの掛け声に■■はごくりと唾を飲み込み、ナイフを自分の疼いてしかたない喉元に突き立て静かに刺した。
「げほッ……ぁ、……ぐァッ……」
「お兄ちゃ──」
「止めるな。お前に止める権利はない」
「──っ」
■■の自傷行為。□□は初対面であるはずのルコンの威圧に怯み止めることができなかった。体は固まり、すぐそばにいるはずの■■に寄り添うこともできずじっと見届けた。
ブスリ、ブスリ、とナイフを刺したところから血が流れる。その血を見るとなぜだか落ち着いた。普通なら死にかねないほどの刺傷なのに、噎せはすれど死ぬ様子はなく無我夢中に刺し続ける。流れていく血と共に、次第に自分の中で渦巻いていた苦しみも流れ出ていくような感覚に溺れ、強張っていた表情も和らいでいった。
「……はぁ……はぁ……」
ルコンが称する野生の血というものが、昂ることで本来の■■の元の姿を呼び起こしたかのような覚醒。その血が抜けたことでいつの間にか張っていた隈のような模様は無くなり、瞳孔の形も元に戻っていた。貧血になり力も抜けたのか、■■はナイフをするりと落とし地面に手をつけ四つん這いになった。
ようやく動けるようになった□□が心配げに■■の顔をのぞき込んできたが、■■は目を合わせまいと顔を背ける。
「……君の知ってる■■はいない。わかっただろ……。早く帰ってくれ。また傷つけてしまう前に……」
「そんなことできないよ……。ずっと一緒って言ったもん……」
「一緒にいたいのは自分じゃない! 君の言ってる『お兄ちゃん』なんていないんだ! 自分は『お兄ちゃん』じゃな……、げほッげほッ!」
叫んだせいで吐血し、■■はバタリと地面に倒れ込んだ。太陽が眩しく■■を照らす。だがそれより、のぞき込んでくる□□の顔の方が眩しかった。
「うそはいらない……もういい……もういいんだ……かまわないでくれ……」
「嘘ってなに……? 私嘘なんて……」
「……今さら、何を……」
「はあぁ。お前はまだ気づかないのか」
わざとらしい大きなため息と共にルコンの呆れの含んだ声が降りかかる。
「きづ、か……」
一瞬何のことかと怪訝に思ったが、ルコンの言葉をきっかけに■■はふと思い出す。
流れる記憶の波を逆らって、脳裏に映し出されたのは人間として初めて目を覚ました時のこと。一人いた病室に入ってきた少女。明るいその子はたしかにこう言った。
『── わたしも一緒だよ』
「ま、さか……」
■■はある可能性に気づき目を大きく見開いた。しかし可能性ではないのだろう。さもなければルコンが口出すとは思えない。それに対し□□は戸惑いながらきょとんと首を傾げている。
「ぁ……、あぁっ……」
「お兄……■■、くん…?」
□□は、■■がお兄ちゃんと呼ばれるのが嫌なのだろうかと思い名前を呼んだが、そういう問題ではないと気づくにはまだあまりに自分のことを知らなすぎた。
「□、□……」
■■は力を振り絞って体を起こし、先ほど無意識に叩いてしまった□□の頬を撫でてからそっと抱き寄せた。
「ごめ、ん……ごめん……ごめんなさい……ごめんなさい……っ……!」
思えば事故に遭った兄が目を覚ましたら記憶喪失になっていたというのに、幼さのわりに取り乱す様子がほとんどなく順応するのが早かった。■■だけでなく□□も特別学級だった理由も、事故の詳細を知らなかったわけも、考えればわかることだった。そして、動物として飼われていた時代をもっと振り返っていれば、あの家に少女なんて存在しないことにも気づけたはずなのに。
〝わたしも一緒〟というのは〝一緒にそばにいる〟という意味ではなかった。〝わたしも同じ境遇〟という意味だったのだ。■■より目を覚ますのが早かっただけで、□□も■■と同じように記憶がないまま目を覚まし、■■と同じように親から先に大まかなことや偽物の知識を植え付けられていたのだとすれば納得がいく。
□□も■■と同じ偽人で、同じ被害者だ。
「久しぶりに兄に会えた感想は?」
しばらくすると、疲れてしまったのか□□に抱きついたまま■■は寝てしまい、ルコンは□□に声をかける。
「……あなたが……お兄ちゃんをこんな目に……?」
「ふふ。いいえ。元を辿れば私のせいになるかもしれないけれど、ぼうやがこうなったのはこの子自身のせい。私は何もしていない」
「……。お兄ちゃん……すごく変わっちゃった……なんでこうなったんだろう……」
「恐かったでしょう? あなたを殺す気だったから当然よね。嫌いになった? 一人で帰る? ぼうやを置いて。いいわよ、それがぼうやの望むことだもの」
何が面白いのだろうか、ルコンは挑発じみながら□□に近づく。
「さあ、選びなさい。無知の者」
何も知らない子に下された選択。□□はキッと目を鋭くしてルコンを睨んだ。
「ふっ。昔と同じ、いい目だ」
ルコンは満足げに嘲笑した。