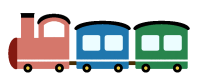少女が目を覚ます頃には道先の大通りでまた人が賑わっていた。誰も彼も必死に客寄せの声を上げている。はて、こんなに人のいる通りまで夜歩いただろうか、そんな疑問符が少女の頭に浮かぶほど脳はまだ眠気から覚めきってはいなかった。
「起きたか」
顔を横に向けると子はパンを頬張っていた。そして半分に折ったパンを少女に差し出し、食べるように促す。少女にはその厚意を拒む理由などなかったし、どこで手に入れたか聞くような野暮なことはしなかった。
「お前名前はあるか」
「……あるけど……教えない」
「なんで」
「……奴隷に名前は必要ないんだって」
「あー、そういう」
「あなたは?」
「……言わね」
「なんで」
「自分と名前が不釣り合いだから呼ばれたくねえんだ」
「……変なの」
拳くらいの大きさをしたパンを子はもぐもぐと平らげるが、少女は米粒でも食べるかのようにちまちまと口に運んでおり食い気のなさがうかがえた。
途中、まだパンを半分も食していないまま少女の手が止まる。それに気づいた子はしかめた顔で少女の顔を覗き込んだ。
「どうした。こういうもんは食えるときに食っとけ」
「……昨日……」
「あ?」
「ごめん……。そのピン、盗もうとして……」
「……。あー……。これな……。別いいよもう気にしてねえ」
「でも盗っちゃった時、すごい叫んでたから……」
少女の言葉に子は顔を渋め、言葉を詰まらせた。たしかに一時我をなくして錯乱していたことには自覚があり、痛いところを突かれたと頭を掻く。
「大事なものだったんでしょ……?」
「……。別に。これ自体はたいしたもんじゃねえよ」
「え。だって……」
「オレは自分の髪が嫌いなんだ。……いや。嫌いっつーと語弊があるな……。とにかく見たくないんだ。せめて視界に入らないようピンで留めてる。それだけ」
「見たくないなら切ればいいのに」
「……簡単に言ってくれるよな。それができたら苦労してねえんだよ」
「ふぅん……」
「親との……、もういいやこの話は。それよりなんで盗もうとしたんだよ」
「……少しは売れるかなって」
「…………」
少女の発言に子は絶句した。貧しさが酷いと金銭感覚も狂うのだろうか。売れるものと売れないものの区別もつかないのか。子は盗みを働いたことに関して怒りを通り越して哀れみを感じてしまう。たしかに少女にとっては、自分より幼いと思った子の所持品を盗むのは簡単だと高を括っていただろう。しかし、それにしても理由が惨めで子は聞いたことを後悔した。
「あのなぁ……こんな何の変哲もない、しょーもねえピンなんてどこ行っても売れねえよ。もし仮に売れたとしたら、母親の元に戻ろうとしてたのか」
「……うん」
「何の足しにもなんねえって……。まあ、金なんかなくても今なら戻れるんじゃねーの? こき使うっつっても召使いが欲しいわけじゃねえし好きにしろよ。国を離れたくねえならなおのこと。うなじの焼き印は布かなんかで隠しとけ」
「戻りたいけど……戻っても迷惑になるだけだから……できない」
「ご飯がなくてもかまわないっつったのお前だぞ」
「お母さんはきっとそうは思わない……」
「はぁーあ、面倒くせえなぁ」
せっかく逃がしてやると選択させているのにその厚意を受け取らず、子は大きくため息を吐いて、頭の後ろで腕を組んで壁にもたれかかった。難しい問題だ、と少女への最善手を一緒に考えることもしないで無責任な態度だ。
少女は子の態度を咎めることはなく、パンを食べ始めようと口に運ぶ。しかしゆっくりと口に運んだパンを食べることはできず、また手元に下ろしてしまった。躊躇っている言葉を吐き出せず、喉の奥でそれが滞留しているせいで食物が喉を通らない。
しばらく黙りとしていたが、少女はふいに言葉を放出した。
「──あなたはどうして親がいないの……?」
その問いに、子は触れられたくないものに触れられたようにぴくりと反応した。すぐに答えが返ってくることはなかったが、承知の上だった少女はじっと子を見つめる。
子は壁にもたれたまま、顔を空に向けたまま、そして冷静になったところでやっと言葉を返した。
「……なんだよ。急に」
「別に言いたくないならいいんだけど……その、昨日は感情的に色々言ってごめん……。私の気も知らないで、って言っておいて、私だってあなたの気なんか知らないのに……自分勝手だったなって……。もしかして私と同じ──」
「同情してんならやめな。オレとお前は違う」
「……違う、って……」
「同情されるような立場じゃねえんだ」
子の雰囲気は変わっていた。周りに敵意を向けた荒々しい態度ではなく、ただ遠くの方へ意識が向いていた。落ち着いたようにも見えるが、それよりも途方に暮れたような、もしくは諦め切ったような、そんな静けさ。その雰囲気から少女はこれ以上言及することはできなかった。ただ一言、
「ごめん……」
それだけを告げた。
目を伏せようやく食を始めた少女を横目で見やり、子はふぅーと長いため息を吐き出すと、頭をボリボリと掻いてから、少女の頭に手を置いた。
「別にいい。気にすんな」
幾度と非情さや冷淡な態度を晒してきたのに、初めて見る慰めと捉えられる行為に少女は目を丸くした。少女が子に顔を向ける頃にはその手は離れてしまったが、くすっと笑う。
「自分より小さい子に頭を撫でられるのなんて変な感じ」
「オレのが年上だっつってんだろ」
「じゃあいくつ?」
「……一〇〇」
「見かけによらず冗談なんて言えるのね」
「冗談じゃな……はあ。じゃあ十二でいいよ」
「なんだ。同い年じゃない」
「……。やっぱり十三」
「ふふっ、変なの」
少女は少し元気を取り戻したようでパンを食べ始めた。子は大通りの先を見つめる。耳に入るのはやはり客寄せの声の雑音ばかり。二人の存在をも掻き消すような雑音に、子は心地良さを感じていた。